masa(masa_aki0917)です。
起きるやいなやこんなツイートを見かけました。
↓
あと小さい頃犬を飼っていて。
明らかに病気なのに、父親がなかなか病院に連れて行ってくれなかった。
母親は免許なくて、連れて行けるほどの距離になかったから無理だった…。
母親犬と息子犬、どちらも同じ病気で天国へ行ってしまった…。
だから無力さにすごい押しつぶされたんだよね。— ほしこ@アイコンは小幸とみさんイラスト🥰 (@hosiko4649) December 14, 2019
「無力さに押しつぶされた」
ものすごく共感することがあり、ふと自分の昔話でもしたくなってムラムラ。
突然で驚かれるかもしれませんが、ぼくは高校1年のとき、ネコを殺しています。
もくじ
捨て猫をひろった日
春先に降る雨ってめちゃめちゃ寒いですよね。
せっかく暖かくなってきた空気を真冬に引き戻すかのようで、冬の疲れに追い打ちをかけるものがあります。
「そいつ」と出会ったのも、そんな冷たいつめたい、春先の雨の日。
「なにか聞こえない?」
強い雨音に混じって聞こえるその声。
気づいたのは、当時付き合ってた彼女。
一度目こそ聞こえませんでしたが、耳を澄ましてみれば、その声はハッキリと確認できるものでした。
ニャアニャアと響くその声は、
可愛らしいネコのそれとは遠く、カラスの鳴き声のようでもあり、壊れたバイオリンのようでもあり、死にゆく断末魔のようにも聞こえ…
姿こそ見えないけれど、その声が「悲鳴」であることは、ぼくも彼女も肌で確信。
高校生にもなった僕と彼女でさえ傘を差してふせぐ、冷たい雨。
それなのにそいつは傘もささず、公園の隅にあるダンボールの中で、小さな体をガタガタと震わせていました。

生後1週間か2週間。
まだ歩くこともおぼつかないような、小さな小さなくろ猫。
ど田舎の公園の片隅に捨てられたそのコは、ただただ何もできず、雨に向かって声を振り絞っていたのです。
不幸にもその声を聞いてしまった僕は子猫をジャージの内側に押し込み、浅はかにも家に持ち帰ることに。
山奥の一軒家、
野良猫が軒先で昼寝をしているような家に住んでいたぼくにとって、「ネコを持って帰る」っていう行為にはあまり抵抗も問題もなかったんですよね。
その日から約15日間、僕と子猫は一緒に生活していくことになります。
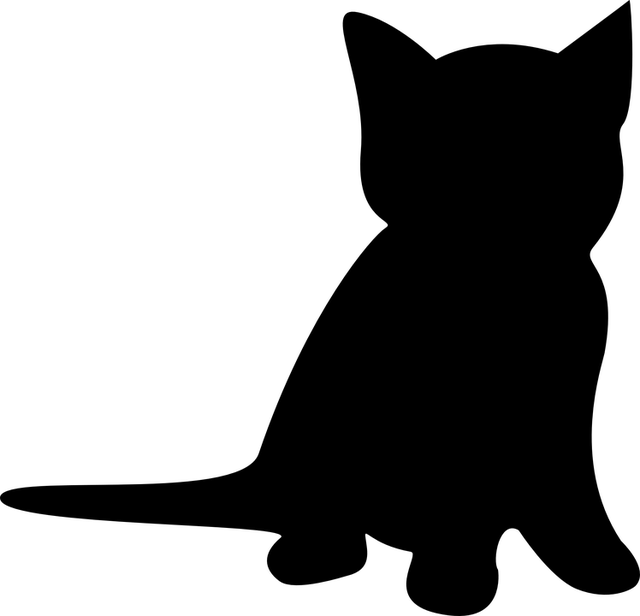
つきっきりの介護
寒い雨に長時間打たれたせいか、それとも元々そうだったから捨てられてしまったのか。
子猫の顔は涙とも鼻水ともつかない液体にまみれ、目は開かず、彼女を呼んだおおきな声すらもはや出ない。
生き物として最低限の呼吸だけをしているような状態。
それでも心なしか子猫は「雨が当たらなくなったこと」を安堵しているようにも見えました。
とにかく体を拭いてやり、毛布にくるみ、ネコ用のミルクを温める。もちろん飲めませんでしたが…。
「どう?」
数日後、子猫の様子を心配した彼女が家に来てくれました。
スマホも持っていなかったので、彼女はウチに来るまで状況を把握することができなかったんですね。
いまにして思えば、見に来るのって怖かったかもしれません。
しかし彼女の心配をよそに、子猫はまだ生きています。
こたつで静かな寝息をたてているところでした。
幸いここ数日の間にミルクを少し飲むようになり、呼べば小さな声を出す程度には回復していました。
相変わらず鼻水も目やにもひどく、目も開かなかったんですが。
子猫が家にいる間、ぼくは一切学校に行かなかった。
自慢することじゃないのですが、とても置いていけるような心境じゃなかったんですね。
かといって何をするかといえば、なにもしてやれません。
ただただ目やにと鼻水をぬぐい、時おり生きているかを確認する。
最近まで中学生だった僕にとって、それ以上なにをどうすれば良いのかもわからなかった。
それでも、目を離したら、カレの呼吸が止ってしまうような気がしてならなかったから。
生きようとする姿
あの朝の喜びはいまでもハッキリと覚えています。
そんな献身的な(?)介護が1週間ほど続いたある日のこと。
いつものように朝起きて子猫の様子をうかがいに行くと、なんと子猫の姿が見当たりません。
冷や汗が出そうになりましたが、すぐにそれは歓喜の想いに変わります。
次に僕の目に映ったのは、自力でヨチヨチ歩く子猫の姿。

※イメージ画像
目もろくに開いてない。
足取りもおぼつかない。
それでも、彼は必死に自力で立ち上がり、フラフラと家のあちこちを探検しているのです。
その喜びと驚きが想像できるでしょうか?
抱き上げて1回落とすだけでも殺せるんじゃないかと思えた小さな体。
骨は浮き出て、どういう仕組みで動いているのかさえわかりません。
でも、自分で歩くことを決めてくれた。
どうにか生きようと再び燃え上がるその命は、いま思い出しても胸に迫るものがあります。
「そうまでして生きようとするんだな…」
意味がわからないけど、そんな風に感じたのが素直なところです。
嬉しくて、嬉しくて。
なんどもネコじゃらしを目の前でちらつかせてみたり、名前を呼んでみたり。
そうそう、名前は前に彼女が訪れた際に決めていました。
呼吸のままならない口から絞り出す鳴き声が「む~…」と聞こえたことから、名前は「むぅ」
「むぅ、こっちおいで」
「むぅ、ミルク飲む?」
1時間ともたなかったけど、むぅは精一杯探検して、ミルクを飲んで。
その日は幸せな気持ちで一緒の布団で眠って。
きっと、明日はもっと元気になる。
あさっては、もっともっと元気になる。
そうそう、こんな話を知っていますか?
「それまでエサも食べられないほど衰弱していた猫が、死ぬ直前に自力で排便したりエサを食べたりする」
猫は自分の死期を悟ると、飼い主にいつも以上に甘えたり、最後の力を振り絞って元気な姿を見せるなどの行動をとることが多いんです
【引用】https://news.livedoor.com/article/detail/15678924/
「ほら、こんなに元気になったよ」とでも言わんばかりのその現象、エンジェルタイムと呼んでいるそうです。
話はそれましたが、
むぅが歩く姿を見たのは、これが最初で最後でした。
夢
あれからむぅは、今まで以上に声も出さず、ひたすら鼻の詰まった寝息をたてるだけとなりました。
お腹が上下していなければ、生きてるかどうかも怪しいほどに。
僕はただ、むうの口に無理矢理ミルクを流し、吐きだしたそれを掃除するという愚行を繰り返すだけ。
「きっと元気になる」
それだけを祈るしかなかった。
大丈夫。一時は元気になったんだから。
きっとまた立ち上がる。目やにも鼻水もなくなる。
きっと大丈夫・・・
ある夜のこと。
そこは雲の中のような、早朝の湖畔のような、霧に覆われた場所。
足下も見えず、霧の中に浮かんでいるような景色。

まるで3Dで合成でもしたかのように、むぅはそこにいました。
夢の中のむぅは涙も鼻水もなく、目もしっかり開いていて。
ずっと一緒にいたのに、むぅの目が切れ長のキレイな造りだったことを、ぼくはそこではじめて知りました。
「むぅ。元気になったの?もう目痛くないの?」
夢の中とは思えない程、空気も、自身の声も、リアルでした。
むぅに近づこうとするのですが、なぜか足が前に出ません。
足下に視線を移そうとしても、むぅから目線を離すことができません。
ゆっくり、深く深く、むぅは一度だけ、ぼくにお辞儀をしました。
ネコが足下にあるエサを食べるときのように、腰を折り曲げて、深く。
むぅの後ろが急に光ったかと思うと、振り向いたむぅはそちらに歩を進めていきます。
足が前に出ないぼくは、それをただ眺めている。
そんな夢。
こうやって書くといかにも作り話みたいで、マンガかなんかの受け売りみたいですよね。
誤解のないように言っておくと、べつに僕は霊感もないし、スピリチュアルも信じないタチです。
この話だって、ひとから聞いたら「おまえ大丈夫?」ってなります。
でも、これは本当にあったこと。
証明する方法も必要もありませんが。
夢から覚めたのは午前4時ごろ。
まだ薄暗い、いつもの布団のなか。
いまでも不思議なんですけど、起きたら顔じゅう濡れていたんですよね。
ずっとずっと、寝ている間、涙を流していたんです。いや、ホント変な話ですが。
すぐそばにいるむぅの体を触るまでもなかった。見なくてもなぜかわかった。
直感的に確信してたから、やっぱりどうかしてたんじゃないかと思います。
めくりあげた布団のなか、
むぅのお腹はもう、
上下には動いていませんでした。
桜の木の下で
寝ている間から考えると、あれほど泣いた1日はありません。
ぼくが乾燥肌なのはきっと、あのときに水分が出すぎたせいだと思っています。
家の裏の山。
見晴らしの良い桜の木の下にむぅを埋めました。
ばあちゃんが言ってくれました。
「あんなに可愛がってもらったんだから、むぅは幸せだったんだよ」って。
じいちゃんが言ってくれました。
「もうどうしようもなかったんだ」って。
ぼくはただただ、
後悔の念で死にたくなっていました。
もっとなにかできたんじゃないか。
助けてあげることができたんじゃないか。
むぅは、苦しかっただけなんじゃないか。
むぅを埋めるその間、涙が止まることはありませんでした。
泥にまみれた腕で、なんどもなんども顔をぬぐって。
とうとう、むぅの目に世界を見せてあげることは叶わなかった。
いつも開かない目で、僕に話しかけてくれていたむぅ。
涙で歪んだ景色は、ずっとむぅが生きていた世界だった。
ひとに捨てられ、それでも僕を疑わずに側にいてくれた。
そんなむぅに、僕はなにひとつしてあげることができなかった。
むぅが言葉を話せたなら、なんて言っただろう。
「違うひとに拾われたかった」
そう、願ったんじゃないだろうか。
ぼくはむぅを埋めて、長い間、その場所にいました。
まだ、もしかしたら、むぅが生きてるんじゃないかって、祈りながら。
おわり
このお話は、まちがっても「オレはこんなに頑張ってネコの世話をした」っていうことじゃありません。
冒頭に書いたように「無力さに押しつぶされた」という話です。
だって普通に考えてみればこういう話ですよね。
「なんで病院連れてかなかったの??」
言い訳をさせてもらうと、当時のぼくにとって「動物病院」って、選択肢になかったんですよね。
両親も祖父母も、基本的に飼い猫を病院に連れて行くなんてしませんでした。
我が家だけじゃなく、20年前の田舎ってけっこうそんな感じなんです。自然に任せるっていうか。
地域にも動物病院なんてなかったし、通学路にもありません。
もしあっても高齢の祖父母は免許を持っていないし、両親はもういなかったし、ぼくには自転車しかない。
考えられないと思いますが、ホントに「思いつきさえしなかった」っていうのが正直なところです。
でもまぁ、控えめに言って愚か者ですよね。
そんな頭の弱い高校生が、いたずらに捨て猫を拾ってきて、ムダに生きながらえさせて、見殺しにしただけ。
あの夢だって、なんにもしてやれない自分の罪悪感が、あるいはむぅに回復して欲しい願望が見せたものなんじゃないかって思うのです。
いま、うちでは懲りずにネコを飼っているワケですが。

このコを飼うときには、本当に何度もためらって、話し合って決めました。
むぅの事を思い出すと、ぬけぬけと他のネコを飼うなんて許されないと思ったから。
どんなに言っても結局は飼ってるんで、なんとも言えませんけどね。
でもこのコを飼うときに、強く強く誓ったことがあります。
「もうゼッタイ、後悔するような飼い方はしない」
ネコの病気と健康に関していろいろ調べ、さらには住まいも移しました。
ぼくがアフィリで稼ぎ、引っ越しまでした背景なんですが…
実はいまのコに不自由させたくない気持ちが原動力になってたりするわけでして。
言い換えたらそれは、むぅへの罪滅ぼしでもあるんですよね。
振り返ってみれば、むぅといた時間は2週間ほど。
それなのに、20年たったいまもなお、強烈にその罪悪感を感じることがあります。
今飼っているネコだって、当時と同じように精一杯可愛がってる「つもり」なのかもしれないですよね。
あの日ぼくが桜の下に埋めた罪悪感は、いまもなお還るところを探して、彷徨っています。
償うこともできず、毎年、春の風にのってぼくの胸をしめつけにくるのです。
無力でなにもできない僕がまだ生きていて、
必死に必死に世界を見ようとしたむぅは、もういません。
むぅに別れを告げたあの場所は、今も春になると、キレイな桜の花を咲かせています。



